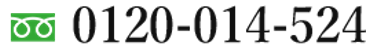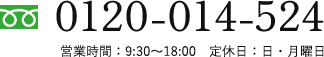NEWS新着情報
棟板金の浮き・釘抜けの原因とビス止め補強について2025.09.18

屋根の頂点部分に取り付けられる「棟板金(むねばんきん)」は、屋根材の接合部を覆い、雨水の浸入を防ぐ重要な役割を担っています。しかし、築年数の経過や環境要因によって棟板金が浮いたり、固定している釘が抜けてしまうことがあります。棟板金の不具合は、放置すると雨漏りや下地材の腐食へとつながるため、早期の点検と適切な補修が欠かせません。

棟板金の浮きや釘抜けの主な原因として、まず「熱膨張と収縮」が挙げられます。金属製の棟板金は、夏場の直射日光で熱を帯びると膨張し、夜間や冬季には収縮します。この繰り返しによって固定している釘が徐々に緩み、最終的に浮きや抜けが生じてしまいます。特に南面や日当たりの良い場所ではこの現象が顕著に見られます。
次に「強風の影響」も大きな要因です。台風や春一番などの突風が吹くと、棟板金に直接風圧がかかり、緩んだ釘が一気に抜け落ちることがあります。最悪の場合、板金自体が飛散し、近隣への被害を及ぼすこともあるため注意が必要です。
さらに「下地材の劣化」も見逃せません。棟板金は通常、貫板(ぬきいた)と呼ばれる木材に釘で固定されていますが、この木材が雨水や湿気で腐朽すると、釘が効かなくなります。特に築15〜20年を超える住宅では、棟板金よりも下地の貫板の劣化が問題の根本となっている場合が多いです。

こうした不具合に対して有効なのが「ビス止め補強」です。従来の釘は一方向に打ち込むだけの固定方法で、時間の経過とともに抜けやすくなる欠点があります。それに対してビス(ねじ)は、螺旋状の溝が木材にしっかりと食い込み、抜けにくい特性を持っています。特に耐候性のあるステンレス製のビスを使用すれば、錆による劣化も抑えられ、長期間安定した固定力を維持できます。
補強の際は、単純に釘をビスに打ち替えるだけでなく、下地材の状態確認が欠かせません。もし貫板が劣化している場合は、新しい樹脂製の貫板や防腐処理された木材に交換した上でビス止めを行うのが理想的です。樹脂製の貫板は湿気や雨水の影響を受けにくいため、メンテナンス周期を大幅に延ばすことができます。

また、ビス止めの際には、棟板金と下地材の間にシーリング材を併用することで、雨水の浸入リスクをさらに低減できます。施工後は仕上げに棟板金の継ぎ目部分もシーリングで処理すると安心です。
まとめると、棟板金の浮きや釘抜けは、熱膨張・強風・下地材の劣化といった複合的な要因によって発生します。放置すれば雨漏りや構造体の腐朽につながるため、早めの点検と補強が不可欠です。特にビス止め補強は、釘に比べてはるかに高い保持力を発揮し、屋根の耐久性を高める有効な方法といえます。定期的なメンテナンスとあわせて、下地材の更新や樹脂材の活用を組み合わせることで、長期的に安心できる屋根環境を維持できます。