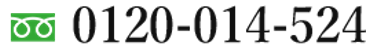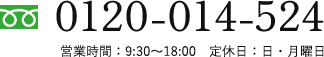NEWS新着情報
瓦の寿命の誤解!?半永久ではない理由を解説します2025.11.26

瓦屋根は「半永久的に持つ」と語られることが多いものの、実際の現場ではこの認識が誤解を招き、メンテナンス時期を逃してトラブルにつながるケースが少なくありません。瓦自体の耐久性は確かに非常に高いものの、屋根を構成するのは瓦だけではなく、下地や防水層、固定金具といった複数の部材で成り立っており、これらの寿命は瓦よりもはるかに短いのが現実です。ここでは、その“半永久ではない理由”をプロの視点で詳しく解説します。

まず理解すべきは、瓦本体は長寿命でも、屋根全体としての寿命は別物という点です。陶器瓦やいぶし瓦は30〜50年以上持つことも珍しくありませんが、その下にある防水紙(ルーフィング)の寿命は一般的に20〜30年しかありません。防水紙が劣化すると、瓦が無傷でも雨水が侵入し、野地板の腐食や室内漏水につながります。そのため、瓦の状態だけを見て「問題なし」と判断するのは危険です。

次に、瓦を固定する役物・釘・漆喰の劣化です。特に棟部(屋根の頂部)は風圧を受けやすく、漆喰のひび割れや剥離、冠瓦のズレが発生しやすい箇所です。これらは10〜20年で点検・補修が必要となり、放置すると台風時に瓦が飛散するリスクが高まります。瓦本体が頑丈でも、固定が緩めば意味がありません。
さらに、地震や台風への耐性も“構造全体”の状態で決まる点も重要です。最新の耐風・耐震基準では、瓦の固定方法(全数釘打ち・ビス留めなど)が厳格化されており、古い施工のままでは基準に合わず、強風でズレや落下が発生しやすくなります。つまり、瓦自体が長持ちしても、施工方法が時代に合っていなければ安全性は確保できません。
そして見落とされがちなのが、瓦はメンテ不要ではないという事実です。確かに塗装の必要はありませんが、棟の積み直し、漆喰補修、割れ瓦の差し替え、谷板金の交換など、定期的なメンテナンスは必須です。谷板金の寿命は15〜25年程度と短く、ここが腐食すると大規模な雨漏りの原因になります。

まとめると、瓦屋根が「半永久」と言われるのは“瓦単体”の寿命の話であり、屋根全体の寿命とは一致しません。プロの現場では、瓦・下地・金具・漆喰・板金といった複数の部材の劣化状況を総合的に判断してメンテナンス計画を立てます。瓦屋根こそ、定期点検と適切な補修を行うことで初めて、その長寿命を活かせる屋根材なのです。